従心会倶楽部の顧問で国際教養大学名誉教授の勝又美智雄先生は、昨年緑内障の悪化で失明され、ご不自由な生活を余儀なくされておられます。
このような中、近況を「風狂盲人日記」として数回にわたってご寄稿いただけることになりましたのでご紹介させていただきます。
今回のテーマは「夏目漱石は売文業の職人」です。
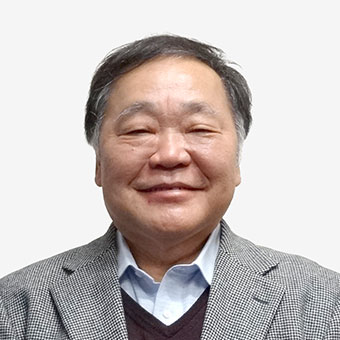
株式会社従心会倶楽部 顧問
国際教養大学 名誉教授
勝又 美智雄 先生
2022年 8月×日
「日本点字図書館」を中心に製作されている朗読CDで夏目漱石(1867-1916)の主な小説を聴いた。30代末に俳句雑誌に書いた『吾輩は猫である』(1905)、『坊ちゃん』(1906)、『草枕』(1906)の3部作は中・高校生時代にも面白いと思ったが、今回聴き直してみても、やはりこれは明治30年代の極めて優れた作品であり、日本近代文学史に残る名作だと頷かされた。
その文才を評価されて、彼は朝日新聞社から破格の高給で文芸部員として雇われ、年に1、2本の連載小説を書き続けることになった。『三四郎』(1908)は東大生の青春の息吹を感じさせるまずまずの佳作と言えるが、『虞美人草』(1907)、『門』(1910)、 『行人』(1912)、『こころ』(1914)などから絶筆となった『明暗』(1916)に至るまでの新聞小説は、どれも読後感の良くないもので、むしろイライラさせられる作品ばかりであり、決して名作と言えるものではないと言わざるを得なかった。
その理由は、主人公が作者の分身のような形で家庭環境、状況設定がわずかずつ異なってはいても、殆ど同じテーマの繰り返しであり、それは主人公が親や親類の財産を当てにして、大学を出てもまともに仕事をしないでのんびり暮らそうという「高等遊民」があれこれ妄想する話に終始しているからだ。主人公の性格は優柔不断で、自分では何も決められず、常に思うことと口にすることと行動の三つがバラバラになっている。精神分裂症的な傾向が強いことだ。
ストーリーで一応のまとまりを見せているのは『こころ』だが、前半は主人公が学生の私、後半が先生の遺書という構成で、繋がりが如何にも悪い。しかも、先生が親友を裏切ったことを悔いて十数年後に自殺するという心の動きが不可解のままに終わっている。また『行人』も主人公と嫂が仲良くしているのを、兄が二人が不倫関係にあるのではないかと疑い、それを試すような小細工をするという話で、結論は何も起こらず、全ての出来事は「コップの中の嵐」に終わっている。
これは、新聞小説だから余りドラマチックなことは書きにくいという面も一部にはあるかもしれないが、実はそうではなくて、漱石自身としては新聞小説を書くことに殆ど情熱を傾けることもなく、ただ原稿用紙をひたすら埋めていけばいい、と考えていた節がある。その証拠に、題名の付け方も文芸部員任せにして、適当に付けてくれという投げやりな姿勢が目立つので、題名だけを見ても中身が何を書いているのか全く分からない、ということにも表れているし、取り分け、元旦からの連載をいつまで書けばいいのかと聞いて「彼岸過ぎまで」と言われると、その言葉をそのまま題名にしてしまうような安直な姿勢が露骨に出ている。
その上、主人公の行動範囲は本郷界隈から日比谷、雑司ヶ谷、田端辺りまでにほぼ限定され、品川、渋谷、浅草、墨田川一帯などの地名はほとんど出てこない。これは、漱石が馴染みの地域だけに主人公を動かしているだけであり、地図や年表、資料類を机に広げながら原稿を書いていた形跡が全く見られないことにも現れている。彼が原稿用紙の横に広げていたのは、恐らく登場人物の簡単な系図や相関関係図程度だったと私は感じた。
漱石はもともと一高・東大出のエリートなのであるが、卒業後は望む東大教員になる道も遠いため、四国の松山にまで「都落ち」し、さらに熊本五高教員になる形で、学生仲間達に比べるとエリートの座から滑り落ちているという挫折感を味わっていた。ロンドン留学も何ら成果もない上、強度の神経衰弱で「夏目が気が狂った」と留学生仲間に通報され、2年で留学費用も出なくなり戻ってくる、という屈辱も味わっていた。帰国後は東大講師(年俸800円)、一高講師(年俸700円)、明治大学講師(年俸300円)として働いた。当時の大卒初任給の平均が月30円(『明治・大正・昭和・平成・令和値段史』 https://coin-walk.site/J077.htm)であったことを考えれば「薄給」とは言えないが、妻に子供が4人いて更に5人目を身ごもっており、女中2人に書生1人を養わねばならず、また家には多くの門下生が集まり来客も多かったので家計は苦しかった。そのため、もっと高給が取れる仕事はないかと思っているところに、新聞社からの誘いがあり喜んで乗ったものであり、月200円の月給に、更に盆暮れに1ヶ月ずつの賞与を加えてもらうことで了承し、年2800円の高給取りで過ごしていた。それだけに、彼の連載した文章も原稿用紙に殆ど字句修正をしたり挿入をしたりすることがなく、1日の分量を書いたら、それをそのまますぐに校正係に回しており、周囲の者が「よくこんな完成原稿が書けますね」と言うと、「完成しなくてもいいんだ。言いたいこと、書き足りないこと、書き直したいことがあれば、それは数日後また同じような話を蒸し返してそこで書けばいい」という、そういう姿勢で終始していた。
漱石は明治の文豪と言われて、今日でも日本で最もポピュラーな作家の一人とされているが、その新聞連載小説の殆どは実は読まれていないのではないか、と私は思う。まともに読むと、余りにも同工異曲が多すぎて辟易としてしまうし、ストーリー展開も殆ど無い。漱石礼賛者の多くは、「近代知識人の苦悩を描いた大作家」と評価しているのだが、私に言わせれば、これは明らかな過大評価であり、本人もまたそんなことは思ってもいなかったのではないか。要するに、原稿用紙1枚幾らと計算しながら桝目を埋めていけばいい、ということに徹することのできた、その作文技術の優れた職人技が目立つだけのものではないのか、と私は強く感じている。
(つづく)
