従心会倶楽部の顧問で国際教養大学名誉教授の勝又美智雄先生は、昨年緑内障の悪化で失明され、ご不自由な生活を余儀なくされておられます。
このような中、近況を「風狂盲人日記」として数回にわたってご寄稿いただけることになりましたのでご紹介させていただきます。
今回のテーマは「団琢磨の孫娘」です。
2022年4月△日
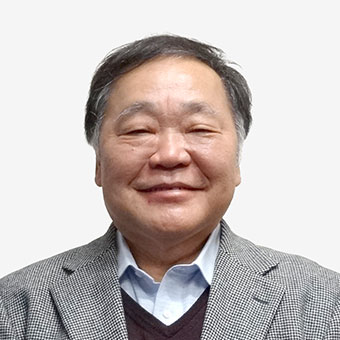
株式会社従心会倶楽部 顧問
國際教養大学 名誉教授
勝又 美智雄 先生
先日、六本木の国際文化会館で、日本語教育のパイオニア的存在だった国際日本語普及協会(AJALT)の理事長、西尾珪子さんの「偲ぶ会」が催された。西尾さんは昨年夏、入っていた老人ホームで家族に看取られ息を引き取った。1932年生まれで享年89歳。戦前の三井財閥の総帥だった団琢磨の孫娘で、1970年代から半世紀以上にわたって独自に日本語教育法を開発し、たくさんの日本語教師を育て、日本に在住する外国大使館の外交官たちや外資系企業の経営幹部たちに日本語を個人授業で教えることを中心に、目ざましい成果を挙げてきていた。
「偲ぶ会」ではコロナの影響のため入場者を制限し、外部者、内部者別に二部にわたって、計約200人が参列、慰霊に献花した。挨拶を依頼された私は、他のゲストが西尾さんの輝かしい業績について詳しく話すだろうと想定し、約5分間、西尾さんの美しい日本語表現がどこから来ているのか、その家庭環境を紹介した。祖父の団琢磨は西尾さんの生まれる五ヶ月前に右翼の宗教団体、血盟団の一員に拳銃で心臓を撃たれて即死したため、西尾さんは祖父の顔は知らない。
父伊能氏は当時西洋美術史を専門にする東大助教授で、流麗な文章の著書2冊を著わしており、将来を嘱望されていた。母は長崎の格式高い高級旅館、上野屋の五女の美智子。幼い時から邦楽に親しみ、和歌を嗜んでいた。そして兄は伊玖磨氏で、戦後日本を代表する作曲家となった。その兄から珪子さんは小学高学年の頃からクラシック・レコードを聴きながら楽譜を読むことを教わり、70代になっても「楽譜を見ればメロディーが頭の中に浮かんでくる」が自慢で、これも兄のお陰と語っていた。珪子さんの4歳年上の姉、朗子(さえこ)さんが珪子さんの日本語の指南役。小学高学年の頃から姉妹で共に新聞の連載小説を愛読しており、特に吉川英治の『宮本武蔵』が大好きだったが、週に1~2回は朗子さんが「珪子、今日の文章はとてもいいから全部覚えなさい」と言って丸暗記することを要求し、姉の言うことには絶対服従の珪子さんがそれに従って必死で覚えると、数時間後に朗子さんが「テストするから言ってごらん」と腕組みをして促す。妹が途中で言いよどんだり、2、3行飛ばしたりすると、すかさず姉が「それでは文章が繋がりにくいでしょ。そこにはこれこれの文章があるはずよ」と言う。妹に命じた後、自分もそっくり暗記していたわけで、姉・妹ともに大変な記憶力の持ち主であり、また日本語の文章の良さ、繊細な表現の面白さを自ずと身に着けるような特訓になった。
さらに、夕食後の団欒のひととき、テレビも無ければラジオもかけず、ひとしきり雑談した後、母が「では、今夜も漢字ゲームをやりましょう」と言って、全員に白い紙と鉛筆を渡し、「 禾(のぎへん)の漢字を2分間で何字書けるか、よーい始め」と言って、ストップウオッチで時間を計りながら書き始める。一番たくさん書いた人が優勝となるが、他の人が書かない漢字を書いた場合ボーナス点が加点され、嘘字を書いた場合には逆に減点になる。これを、「次は阝(こざとへん)、次は下に心が付く漢字」などと言って、幾つかゲームを続ける。これでトップは常に朗子さん。母と珪子さんが二番手争いで、兄は妹二人に勝たせようと余裕を持っていたせいか、ゆっくりと焦らずに字を書き、父もしきりに首を捻っては書いていく。その父が毎回のように尤もらしい漢字を書くので、その度に娘二人が「そんな字はない」と手元の漢和辞典でチェックする。父は「そうかな。あると思ったけどな」と首をひねるのだが、どうやら場を和ませ、家族全員を楽しませ笑わせようと意図的にありそうでなさそうな漢字をひねり出すことに腐心していたようだ。
こうした日本語の訓練を幼い時から浴びていた珪子さんが、学習院大3年の時に1年間で書き上げた卒論は『道行の研究』。万葉集から新古今和歌集、連歌を経て、江戸時代の近松門左衛門の心中物に至るまで、義理と人情の板挟みで心中せざるを得なくなった男女の哀切感漂う思いを切々とした文章でつづる道行の系譜を辿った力作で、指導教官からも激賞された。3年生の時に1年間で資料を調べ書き上げたというその卒論を借りて読んでみたところ、400字詰め原稿用紙約200枚を綴じていて、最初から最後までマス目にきっちり楷書で綺麗な字体で書いていて、ほとんど乱れがない。今読んでみても、大学院レベルの論文に相当するような質の高いものだった。
こうした日本語の豊かな蓄積があってこそ、日本文化の支えとなる日本語表現の美しさを人一倍強く意識し、それを外国人にも広く知ってもらおうとしてAJALTを設立したということが実に良く分かるのだ。
西尾さんの講演やシンポジウムなどに同席してその発言を何度も聞いているが、常に起承転結が明確で、論旨明快、歯切れがよく、しかも当意即妙の冗談も加えながら聴衆を引っ張り込んでいく力は大変なもので、大体制限時間いっぱいに終える巧みさもなかなか余人には真似ができない芸当と言えた。そうした日本語を駆使する力があるからこそ、その伝統を受け継いだAJALTが、文化庁や各国の外交官、大企業の外国人・日本人を問わず「こんなに美しい日本語を駆使するAJALTの人たちなら、安心して仕事を任せられる」と信頼され、今日の隆盛を築いたと言えると私は確信しているし、西尾さんの創った伝統を引き継いでいく限り、AJALTはこれからも大きく発展していくことだろうと信じている。
―― ということを大体述べたのだが、後で何人もの人が「とてもいい話で良かった」と喜んでくれたのは、私自身とても嬉しかった。(つづく)
